弁護士石井です。
令和8年4月から16歳以上の自転車運転者に「青切符」が適用されると報道されています。
自転車への規制は厳しくなる方向ですね。
自転車規制強化の背景
令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者に対して交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
これまでは注意で終わるか、刑事手続きという選択でしたが、反則金の選択肢が出てきたので、一定額を支払わされる人が増える可能性があります。
背景には、自転車関連事故の深刻化があると言われます。令和6年中の自転車関連事故は約6.7万件発生しており、決して少ない数字ではありません。
数年の推移を見ても、緩やかな増加傾向が見られます。
車道通行原則と事故の実態
自転車は法律上「軽車両」であり、車道通行が原則とされています。
歩道を走れば歩行者との事故リスクが高まるため規制が強化されたように感じますが、車道の通行ルールもわかりにくいところが多いです。
車を運転していれば、車道走行の自転車は、バイク以上に危ないと感じますし、自転車で車道を走行していると、車のジャマになっていると感じることも多いです。
自転車の死亡・重傷事故における相手当事者の約75%が自動車です。
興味深いのは、事故類型の詳細です。 自動車との事故のうち、出会い頭衝突が約55%で最も多くなっています。
これは交差点での接触が多いことを意味しており、単純に車道を直進している際の事故ばかりではないことがわかります。
出会い頭衝突が最多という現実
出会い頭衝突が最も多いという事実は重要です。
これらの事故では、自転車側にも安全不確認や一時不停止等の違反が多く見受けられます。
つまり、車道通行そのものよりも、交差点での安全確認不足が大きな要因となっているといえます。
車道を通行していても、交差点で適切に一時停止し、安全確認を行えば、この種の事故は防げる可能性があります。
逆に言えば、歩道を通行していても、車道に出る際の安全確認が不十分であれば、同様の事故リスクが存在します。
この点から一時停止違反の規制が強くなる可能性はありそうですね。
法改正が事故に与える影響
青切符制度の導入により、自転車利用者の法令遵守意識の向上は期待されます。
特に信号無視、一時不停止といった基本的な交通ルール違反への対応が強化されることで、出会い頭衝突の減少につながる可能性があります。
ただし、規制強化だけでは限界もあります。 車道通行を徹底するのであれば、自転車専用レーンの整備や、運転者への自転車に対する注意喚起も並行して進める必要があるでしょう。特に自転車専用レーンが整備されていない道路では、より注意深い運転が求められます。
自転車と歩行者の事故
意外に自転車と歩行者の事故での相談を受けることが多いです。
自転車運転者が保険に入っていないと大変なことになります。
自転車が歩道を走れるルールとしては、
○ 道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき
○ 自転車の運転者が、高齢者や児童・幼児等であるとき
○ 車道又は交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
とされていますが、歩行者は優先。子どもや高齢者に衝突させて大怪我させたら、賠償金も高額になります。
私自身、自転車に乗るものの、車道が危ないときに歩道を利用しています。歩行者が多いときは怖いので降りて歩行者扱いにしています。1車線でバスとかの大型車両に抜かれるとき、怖いんですよね。
このときの主張としては、通行安全を確保するためやむを得ないというものになりますね。青切符規制が始まったら、このあたりの解釈が詰められるのでしょうか。
まあ、余計なお金を払わないように基本ルールは確認しておきましょう。
https://www.npa.go.jp/news/release/2025/rulebook.pdf
規制強化の話もあり、自転車を卒業しようかという気持ちも出てくるのですが、一方で、自転車は認知症リスクを低下させるという話もあり、悩むところです。
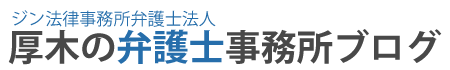



コメント