弁護士石井です。
人手不足倒産が増えているとの記事をよく見かけるようになりました。

企業が従業員を引き止められないことで経営破綻する従業員退職倒産も増えているとか。
実際に、好況と言われる分野の中小企業でも人が来ないから事業が回らず倒産という相談も多いです。
従業員退職型倒産の急増と最新データ
記事によれば、2024年に判明した人手不足倒産は342件。
そのうち従業員や経営幹部の退職が直接・間接的に起因した「従業員退職型」の倒産は87件に達したとのこと。
前年(67件)から約3割増加しただけでなく、多くの産業で人手不足感がピークに達した2019年(71件)をも大幅に上回り、集計が始まった2013年以降で最多とのこと。
この数字が示すのは、単なる人材不足ではなく、既存の従業員の流出が企業存続の危機に直結する時代が到来したということです。
サービス業が全体の35.6%を占める最多業種に
2024年の従業員退職型倒産を業種別に見ると、最も多いのは「サービス業」で31件、全体の35.6%を占めています。サービス業が最多となるのは2019年以来5年ぶりとのこと。
特に目立つのは
– ソフトウェア開発などのIT産業
– 人材派遣会社
– 美容室
– 老人福祉施設
とされています。
これらの業種は元々人材の定着率が他産業と比較して低い傾向にあり、慢性的な人手不足に悩まされています。
建設業・製造業・運輸業でも急増
次いで多いのが「建設業」で18件。設計者や施工監理者など、業務遂行に不可欠な資格保持者の退職により、事業継続が困難になったケースが目立ちます。
また、「製造業」や「運輸・通信業」では初めて年間10件を超え、工場作業員やドライバーの退職によって事業運営がままならなくなったケースが相次いでいます。
このあたりの業種では、固定費も高い傾向にあり、人手不足で一気に資金繰りが厳しくなるということもあります。
賃上げ格差が生む二極化の問題
現在の状況がより深刻なのは、長期化する物価上昇によって従業員からの賃上げ要求が強まっている点です。大企業では継続的な賃上げを実施する動きが広がっていますが、中小企業の間では対応に格差が生じています。
収益力がある企業は積極的に賃上げを行う一方、「無い袖は振れない」と賃上げができない中小企業も多く、賃上げ対応の二極化が進行。
この格差は人材の流動化をさらに加速させる要因となっています。
賃上げができないことを理由に従業員が辞めることで経営が行き詰まる「賃上げ難倒産」が今後は増加していくことになりそうです。
多くの未来予測本でも、このあたりの中小企業が淘汰されていく話が書かれています。
弁護士事務所も縮小なのか
ジン法律事務所弁護士法人でも、昨年、求人をかけたのですが、個人事業主時代を含めて過去一番うまくいかない状況でした。知り合いの税理士とかも、同じようなことを言っていました。
マーケティング会社からは人材確保のため売上増加セミナーのDMが来ています。
価格の相場感がある士業は、価格転嫁で単純に売上増加をしにくいところがあり、人手不足倒産まではいかなくても、人手不足による縮小はありそうな気がしています。
ふと地元を見渡したら、支店を大展開していた弁護士法人が事業譲渡で他の法人に切り替わっていたり、たくさん弁護士が所属していた弁護士法人が全支店閉鎖して弁護士1名になっていたことに気づきました。
なんか、乗り遅れている?私が気づいていない何かが起きているのでしょうか。
厳しい業界の社長さんからも、社会保険、消費税、インボイス。こんな状況で人を雇用できないという声もよく聞きます。たしかに、小規模事業者が売上最大化を目指しても、あまりいい事がなさそうな構造ですよね。
Googleさんの変更も秒読みのようですので、しっかり時代を見極めようと思います。
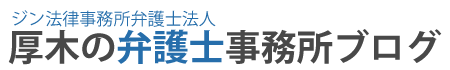
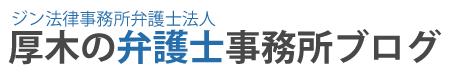
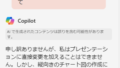

コメント