弁護士石井です。
ガーシー元議員の裁判で公示送達が話題になっていました。
裁判では郵便で書類を送る必要があります。住所がわからないと送れません。住所不明でも使えるのが公示送達という方法です。
しかし、ネット上で活動している人には、DMなどで連絡を入れておかないと、この公示送達は使えない可能性が高いと判断されました。
公示送達とは何か
公示送達とは、裁判所から相手に送るべき訴状などの書類を直接届けられない場合に、裁判所の掲示板に「書類を保管しているので受け取りに来てください」という告知を掲示することで、法的に送達が完了したものと扱う制度です。
民事訴訟法第110条以下に規定されており、「相手に書類を届けたいが居場所がわからない」ときの最後の手段という位置づけです。
公示送達が必要となるケース
私の経験上、公示送達が利用される典型的なケースは以下のとおりです。
1. 相手の所在不明
・不動産の明け渡し請求で被告の転居先がわからない場合
・貸金返還請求で債務者が引っ越して行方不明になった場合
・配偶者が失踪して連絡がつかない離婚訴訟
実際に、行方不明の配偶者を相手にした離婚裁判では、公示送達により訴状を送達して欠席裁判で離婚判決を得るケースがあります。
2. 海外送達の困難
・相手が海外に住んでいて送達嘱託ができない場合 ・国交のない国に住む相手への訴訟
このような場合、通常の方法では書類を送ることができないため、公示送達が唯一の手段となります。
公示送達の手続きの流れ
申立ての段階
公示送達を行うには、まず裁判所に申立てが必要です。この際、以下の資料を提出します。
・相手の住民票や戸籍附票
・郵便が返送された封筒
・所在調査を行ったことを示す報告書
裁判所は提出資料を厳格に審査し、本当に相手の所在が不明かどうかを確認します。私の経験では、裁判所から追加の調査を指示されることも珍しくありません。
現地訪問、隣家への聞き取りなどが必要になることも多いです。
公示送達対応の調査会社もいます。
掲示の実施
許可決定が出ると、裁判所の掲示板に告知文が掲示されます。掲示内容は訴状の全文ではなく、「書類を裁判所で保管しているので交付を受けてください」という告知です。
掲示期間は原則2週間(相手が海外にいる場合は6週間)で、この期間が経過すると法律上送達が完了したとみなされます。
裁判の進行
公示送達の効力発生後は通常どおり裁判が進行し、被告が出廷しなければ欠席のまま審理が行われます。判決も同様に公示送達で送達され、判決書掲示の翌日から2週間経過で判決が確定します。
公示送達の問題点とリスク
相手が知らない可能性が高い
公示送達の最大の問題は、相手本人が実際にその事実を知る可能性が極めて低いことです。
掲示板に掲示するといっても、当の相手やその知人が偶然裁判所に立ち寄って掲示を目にしない限り、まず気付かれることはありません。
無効となるリスク
公示送達が適法に行われなかった場合、手続き自体が無効となる可能性があります。
東京高等裁判所平成21年1月22日判決では、被告会社の営業所への送達を十分検討せずに公示送達を行った事案で、「営業所への送達が可能だったはずだ」として公示送達を無効と判断しています。
ガーシー事件の概要
元兵庫県警警察官の男性が、ガーシー氏のYouTube動画で「ヤクザと賭けマージャンしてクビになった」などと発言され、名誉を傷つけられたとして1千万円の損害賠償を求めた事件での報道がありました。
公示送達が無効とされたものです。

1審の神戸地裁では、公示送達により判決。ガーシー氏も出廷せず、請求通りの1千万円の支払いが命じられました。しかし、大阪高裁は、この1審判決を取り消し、審理を地裁に差し戻すという判断を下しました。
公示送達の問題点
公示送達制度
公示送達は、当事者の住所が不明な場合に、裁判所などに一定期間書類を掲示することで、法律上「届いた」とみなす制度です。
従来は、住民票の住所に送達できない場合、「手段を尽くして探索したが分からない場合」に限って公示送達が認められていました。
今回の問題
ガーシー氏のケースでは、住民票の住所から引っ越していたため呼び出し状が届かず、公示送達での手続きとなりました。本人は判決報道で初めて訴訟を知ったという状況でした。
地裁は公示送達の手続きを行いましたが、高裁はこれを違法と判断しました。
大阪高裁の判断
SNSでの連絡義務
高裁は、DMでの連絡は「通常期待される手段」だと判断しました。通常期待される手段であるDMでの連絡も試みていないのだから公示送達が使えるレベルではなかったという判断です。
これは、SNS時代の新しい連絡手段を法的に認めた判断といえます。
判決の理由
公示送達は当事者の住所などが「手段を尽くして探索したが分からない場合」に限られると指摘。
SNSのDM機能での連絡を行わずに実施した公示送達やその後の判決は違法だと結論付けました。
実務への影響
弁護士実務の変化
この判決により、今後の訴訟では、相手方にSNSアカウントがある場合、DMでの連絡も「手段を尽くした探索」に含まれる可能性が高まりました。
特に、YouTuberやインフルエンサーなど、SNS上で活発に活動している人を相手にする訴訟では、DMでの連絡が必須となるかもしれません。
「あなたに対して、裁判を起こしたいんだけど、住民票上の住所にいないみたいですね。どこに送れば届きますかー?」みたいなDMをしておく必要があるのですね。有名人がこんなDMで教えてくれるのでしょうか。

これが無視され続けたり、ブロックされたりしたら、その内容を報告書にまとめるのでしょうね。
このDMは誰から送るのか、依頼者なのか、弁護士アカウントなのでしょうか。
弁護士業務としてSNSも頑張らなければならなさそうです。
まあ、有名人の場合、DMに限らず、法人経営をしていることも多いでしょうから、そっち方面の調査も必要でしょうね。
送達制度の課題
民事裁判の送達制度は、住民票の住所に基づく郵送が基本でした。しかし、実際の居住地と住民票の住所が異なるケースが増えている現代では、この制度の限界が露呈しています。
SNS時代に対応した送達制度の整備が急務となっています。
現行法の枠組みでは対応しきれない部分があり、法改正による制度の見直しが必要という声もあります。
いつまで紙でやるかという問題もあるでしょう。
まとめ
この判決は、ウェブ時代の裁判手続きに関する重要な判断といえます。
有名人に対して、公示送達が無効となるリスクが高まる判断です。
SNSでの連絡をどこまで義務化するのか、どのような連絡を入れれば公示送達が使えるのか実務に与える影響も大きいと感じます。
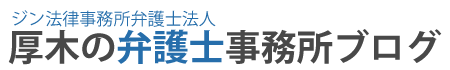


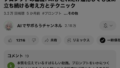
コメント