弁護士石井です。
夫婦の同居義務についての裁判例の紹介です。
福岡高裁平成29年7月14日決定になります。

夫婦の同居義務を否定した判断です。
事案
夫と妻が別居した。
妻から夫に対して離婚請求、夫は争う。訴訟。
高裁で婚姻関係は破綻までしていないとして離婚請求が否定された。
婚姻関係が破綻していない結論となったので、夫としては破綻していないのであれば同居の義務があると主張。
同居を求める審判の申立。
判断内容
家庭裁判所は同居を命じる審判。
妻が即時抗告で不服申立て。
高等裁判所では、同居義務を否定という結論です。
夫婦の同居義務に関しては裁判例でも分かれていたりしていて、諸般の事情で同居を命じることが個人の尊厳に反しないかどうかなどの視点で判断されています。
婚姻関係破綻のレベルとして、離婚はできないけど、同居までは命じられないというゾーンがあるわけですね。
今回のケースでは、妻が夫をストレッサーとする適応障害であることなどから、夫との同居は強制できないという結論をとったようです。
配偶者と復縁したいという申立を考えている方はチェックしておきましょう。
(1) 抗告人と相手方は夫婦である以上,一般的,抽象的な意味における同居義務を負っている(民法752条)。しかしながら,この意味における同居義務があるからといって,婚姻が継続する限り同居を拒み得ないと解するのは相当でなく,その具体的な義務の内容(同居の時期,場所,態様等)については,夫婦間で合意ができない場合には家庭裁判所が審判によって同居の当否を審理した上で,同居が相当と認められる場合に,個別的,具体的に形成されるべきものである。そうであるとすれば,当該事案における具体的な事情の下において,同居義務の具体的内容を形成することが不相当と認められる場合には,家庭裁判所は,その裁量権に基づき同居義務の具体的内容の形成を拒否することができるというべきである。
そして,同居義務は,夫婦という共同生活を維持するためのものであることからすると,共同生活を営む夫婦間の愛情と信頼関係が失われる等した結果,仮に,同居の審判がされて,同居生活が再開されたとしても,夫婦が互いの人格を傷つけ,又は個人の尊厳を損なうような結果を招来する可能性が高いと認められる場合には,同居を命じるのは相当ではないといえる。
そして,かかる観点を踏まえれば,夫婦関係の破綻の程度が,離婚原因の程度に至らなくても,同居義務の具体的形成をすることが不相当な場合はあり得ると解される。
(2)ア 本件において,もともと抗告人が相手方との別居を開始したのは,相手方の両親との不和に原因があったものと思われるが,その後,相手方との話合いが繰り返される中で,その内容が,相手方実家での同居,別の場所での同居,離婚といった経緯をたどるうち,上記離婚訴訟の判決に至るまでの間に,抗告人の相手方に対する不信感,嫌悪感が強まっていき,前記のとおり,現時点で,抗告人は,適応障害の症状を呈しており,そのストレッサーとされるのが相手方であることは明らかである。
この点,相手方は,自身はストレッサーではなく,相手方との紛争状態こそが抗告人のストレス原因であると主張する。しかしながら,抗告人について,調停において相手方と同席した際にのみ身体症状が現れていることなども踏まえると,紛争状態の継続が抗告人の適応障害の背景にあることは否定できないとしても,ストレッサーとなっているのは,相手方自身あるいは相手方との関わりであるというべきである。
また,相手方が作成している書面の内容からは,相手方において,面会交流のあり方を含めた長女との交流について強いこだわりを有していること,それが,長女を監護している抗告人との同居を求める大きな動機になっている様子はうかがわれるものの,抗告人自身の体調などに対する労りといった心情などはうかがわれず,相手方が,抗告人から嫌悪されていることを自覚している様子がうかがわれる。
イ かかる事情を踏まえると,抗告人について,あらかじめ薬を服用することで適応障害の症状を抑えることができる可能性はあるとしても,そのようにしてまで相手方との同居生活を再開したところで,抗告人において,早晩,服薬によって症状を抑えることも困難となり,再度別居せざるを得なくなる可能性は高いということができ,上記相手方の作成した書面の内容や,これまで当事者双方が互いに批判的で疑心暗鬼の状態にあることに照らすと,そのような事態に至った時に,相手方から抗告人に対し,適切な配慮がされるとは思われず,相互に個人の尊厳を損なうような状態に至る可能性は高いといわざるを得ない。
(3) また,本件においては,抗告人が提起した離婚訴訟において,いまだ婚姻を継続し難い重大な事由があるとまでは認められないとして抗告人の請求を棄却する判決が平成28年■月■日に確定しているものの,控訴審判決は上記の別居期間が,抗告人と相手方において共に生活を営んでいくのが客観的に困難になるほどの長期に及んだものとはいえないとし,婚姻関係の修復の可能性がないとまではいえないことから抗告人の離婚請求を棄却したにとどまるものであって,抗告人と相手方の婚姻関係は,上記判決の時点でも既に修復を要するような状態にあったことは,明らかである。そして,控訴審における弁論終結の時点で,婚姻期間中の同居期間が約3年10か月であるのに対し,別居期間は約2年7か月に及んでおり,その後,抗告人の相手方に対する不信感等は,相手方自身をストレッサーとして適応障害の症状を呈するほどに高まっている。そうすると,抗告人と相手方の夫婦関係の破綻の程度は,離婚原因といえる程度に至っていないとしても,同居義務の具体的形成をすることが不相当な程度には至っていたというべきである。
(4) 以上に述べた諸事情を踏まえると,現時点において,抗告人と相手方について,同居義務の具体的内容を形成するのは不相当と認められる状況にあるということができる。
原審判は,抗告人に対し,相手方による住居地の確保という条件付きで同居を命じたものであり,その調整の間に夫婦関係が改善することを期待したものと解されるが,原審判の主文に定める住居地の確保自体は,終局的には相手方が独断で決定することが可能なものであり,その決定に当たり当事者間で話合いが十分に行われる保証はなく,そのような場合に両者の関係改善が見込めるとはいい難いのであるから,かかる条件付きであっても,やはり現時点で,抗告人に対し,相手方との同居を命じるのは相当ではない。
相手方自身が,抗告人について,治療を行って心と体の健康を取り戻し,まずは普通に話せるように治ってから今後のことを一緒に考えてもらえないか相談させていただけないかとも述べている(平成29年■月■日付け主張書面10,11頁)ことも踏まえると,抗告人に身体症状まで現れている現時点においては,当面は抗告人の心身に配慮してその意向を尊重し,別居状態を維持した上で,長女の面会交流等を円滑に行う中で,徐々に夫婦間の信頼関係を醸成していくといった形で,円満な夫婦関係の回復の道を探るのが相当と思料される。
なお,離婚訴訟における控訴審判決のなお書きは,抗告人に対し,離婚の合意に至る努力のみを望むものではないし,相手方に対して,控訴審判決があるからといって,自己の正当性のみを主張することを許容するものではない趣旨のものと解されることを付言する。
(5) 以上のとおりであるから,条件付きであるとはいえ,現時点での同居を命じた原審判は相当ではなく,取消しを免れない。
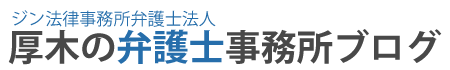





コメント